|
今回は趣向をいくつか、順番に紹介することにします。本の写真がついていない理由もそこで。
1)この本は、小説でもハウツーものでもなくて、戯曲です。めずらしいでしょう。
小説を読んでその世界に入ると、ヒーローなりヒロインなりに感情移入したうえで、その世界を好きなように想像していっしょに動き回る印象です。ところが戯曲ではその場面が細かく指示されて、どこからどう歩いて、どうしゃべるかまで明らかにされています。それでもそこに自由があって、あたかも脚本、演出家にでもなったようにその世界を作れるのです。読んだ時の楽しみ方が少しばかり違うようですが、面白ければそれでいい。
2)この話は文句なしに面白い。有名な話ですから、少しばかり筋書きを紹介しても許されるでしょう。
第二次世界大戦直前のアメリカ。ブルックリンの豪邸に暮らす老姉妹は、貸間を探して訪れた老人に毒入り酒を振舞って、天国に送ることに精を出していた。自分をマッカーサーと思い込んでいる甥も同居。そこへ、もう一人の甥が新妻を連れてやってくる。さらに、その兄が久しぶりに帰郷してとんでもない展開へ。
これまで小説を避けてきたのは、好みの違いで面白くないのは申し訳ないからですが、これは文句なし。日本の話ではあまり登場しない「老嬢」ですが、ミス・マープルを筆頭に、小説でもTVシリーズなどでも活躍しています。
3)映画で見た人もいるでしょう。ケイリー・グラント主演で、原作に忠実に作られています。実のところ、小生も映画を先に見て、読んだのはその後。本当は舞台を見ておきたいところですが、これまでその機会に恵まれておりません。映画にするととたんに面白くなくなる小説(日本だと顕著で、山田風太郎や半村良など、被害者は数多く)がたくさんありますが、これは映画でもちゃんと面白い。もちろん原作がよく作られていることもありますが、監督の腕が問題でしょう。さらに役者がよかった。舞台で受けたのと同じように、映画でも藝達者です。
4)これは本を読んだのではなく、青空文庫から入手したものです。知らない?ウェッブ上の電子図書館で、著作権の切れたものを中心に数多くの作品が入手できます。この話もインターネットからダウンロードして、適当に整形した上でパームパイロット(PDA)に載せて、細かい空き時間に読みました。必要なら
青空文庫までお出かけ下さい。本を読む時間もない、という人でも待ち時間5分とか、空き時間3分とかあるでしょう。そんな時でも、文庫本を取り出す代わりにPDAで読むという芸当ができます。図書館から借りるのと同様に無償で、返却期限もありません。気軽に利用できると思います。
例えば、夏目漱石、芥川龍之介、海野十三、島崎藤村、寺田寅彦、テレンス・ラティガン、こんなところを青空文庫で読んでいます。
5)どうしても本当の本の形で読みたかったら、ちゃんと出版されています。手配すれば買えるでしょう。訳者は違いますが。どうせならビデオ(DVD)でも借りて見てもいいかもしれません。楽しみ方はそれぞれ。
|
 人の心をゆさぶるに十分なほど、生命を感じるほどの力がこもった作品というのがあります。詩歌の件もあったけれど、書籍にも同じ力を感じるものです。内容も、著者の力量も、そして主張の強さそのものも。そこらにある書き散らしただけの本、書の名に値しないような出版社御用達のなれあい文書、独りよがり以上のものではない単なる作文の類の多いこと。この本はそんな中で燦然と輝いていると言っていいでしょう。
人の心をゆさぶるに十分なほど、生命を感じるほどの力がこもった作品というのがあります。詩歌の件もあったけれど、書籍にも同じ力を感じるものです。内容も、著者の力量も、そして主張の強さそのものも。そこらにある書き散らしただけの本、書の名に値しないような出版社御用達のなれあい文書、独りよがり以上のものではない単なる作文の類の多いこと。この本はそんな中で燦然と輝いていると言っていいでしょう。 これまでは普通の本を選んできましたが、今回は専門分野のものです、すんません。え?これまでも偏ってたって? 十分に「普通の本」だったつもりなんだけどなぁ。どうせ趣味の世界よ。ま、確かに今回は小生の仕事に関係するところなのです。
これまでは普通の本を選んできましたが、今回は専門分野のものです、すんません。え?これまでも偏ってたって? 十分に「普通の本」だったつもりなんだけどなぁ。どうせ趣味の世界よ。ま、確かに今回は小生の仕事に関係するところなのです。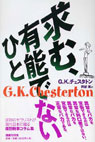 あのブラウン神父のチェスタトン。とは言うものの、じつのところブラウン神父ものは読んだことがない。これは、辛口批評でなるコラムニストのチェスタトンであり、こちらの方が本職だとか。
あのブラウン神父のチェスタトン。とは言うものの、じつのところブラウン神父ものは読んだことがない。これは、辛口批評でなるコラムニストのチェスタトンであり、こちらの方が本職だとか。 これまで何冊か紹介してきましたが、小説の類は出していません。「お話」というのは好みの問題であり、一般向けに大丈夫というようなものにはなかなか当たらないものです。個人的な好みだけであれば、かなりの候補があるのですが。そこで今回は、その小説を読むための見方の一つである、「名文」とか「小説論」とかいう分野の本です。
これまで何冊か紹介してきましたが、小説の類は出していません。「お話」というのは好みの問題であり、一般向けに大丈夫というようなものにはなかなか当たらないものです。個人的な好みだけであれば、かなりの候補があるのですが。そこで今回は、その小説を読むための見方の一つである、「名文」とか「小説論」とかいう分野の本です。 帯に曰く:
帯に曰く: 国語、英語、社会、数学、ときて今回は理科(科学)であります。
国語、英語、社会、数学、ときて今回は理科(科学)であります。 4色問題とフェルマの最終定理、この二つの難問が解決したのはつい先日のような20世紀末。数学の世界も進歩し続けているのですねぇ。その20世紀の数学の歴史をそのまま表しているような人物がこのエルデシュです。聞いたことがない?そうでしょう、小生も同じ。
4色問題とフェルマの最終定理、この二つの難問が解決したのはつい先日のような20世紀末。数学の世界も進歩し続けているのですねぇ。その20世紀の数学の歴史をそのまま表しているような人物がこのエルデシュです。聞いたことがない?そうでしょう、小生も同じ。 日本の歴史に関して、歴史学者も一般人(パンピー)も、悪癖に毒されています。それは、軍記物、講談、歌舞伎を本当の歴史だと思いこんでいること。だからありえないことを平気で並べ立てるのです。
日本の歴史に関して、歴史学者も一般人(パンピー)も、悪癖に毒されています。それは、軍記物、講談、歌舞伎を本当の歴史だと思いこんでいること。だからありえないことを平気で並べ立てるのです。 中学校英語の最初の一歩はIPA(発音記号)だった。この事実は、その後の英語に対する興味、進歩、態度に決定的な影響を与えました。さすがは附中。賢明なる諸姉諸兄とは違ってあいにく察しの悪い生徒にはその重要性が分かるはずもなく、先生の偉さも理解できず、気が付いたのはずいぶん後になってからですが。
中学校英語の最初の一歩はIPA(発音記号)だった。この事実は、その後の英語に対する興味、進歩、態度に決定的な影響を与えました。さすがは附中。賢明なる諸姉諸兄とは違ってあいにく察しの悪い生徒にはその重要性が分かるはずもなく、先生の偉さも理解できず、気が付いたのはずいぶん後になってからですが。 係り結びの法則、覚えているでしょう。あれは古文だから、日本語じゃぁない、と思うかもしれないけれど。学校文法では、「何かの強調」として覚えていたあの係り結びの本質は、単に文節の切れ目を示す印だった、という主張。
係り結びの法則、覚えているでしょう。あれは古文だから、日本語じゃぁない、と思うかもしれないけれど。学校文法では、「何かの強調」として覚えていたあの係り結びの本質は、単に文節の切れ目を示す印だった、という主張。